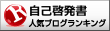2017年に読んだ本のなかで3本指に入る激推し本!【コピー1枚取れなかった僕の評価を1年で激変させた7つの仕事術】
スポンサードリンク

この名著が今ならKindle Unlimitedなら無料で読めますよ〜
急いで下さい!
※2018.9月1日現在
- 評価を1年で激変させる
- なぜ仕事ができないのか
評価を1年で激変させる
みなさん、仕事やブログ頑張っていますか〜
私は仕事もブログも頑張っていますが、結果がなかなか出てきません・・・
やはり、先人の知恵・現在活躍している人の知恵を拝借するのが、1番の近道だと思います。
そんなわけで、読書というのはまさにその知恵を拝借するには持って付けだと思うのです。読んで読んで、実践して実践してと繰り返すのが、力もつき、知恵もつくのかと。
今日はそんな仕事もできて、ブログでも活躍しているShinさんの1冊をご紹介したいと思います。
早速行ってみましょう!

コピー1枚とれなかったぼくの評価を1年で激変させた 7つの仕事術
- 作者: Shin
- 出版社/メーカー: ダイヤモンド社
- 発売日: 2017/07/07
- メディア: Kindle版
- この商品を含むブログを見る
![コピー1枚とれなかったぼくの評価を1年で激変させた 7つの仕事術 [ Shin ] コピー1枚とれなかったぼくの評価を1年で激変させた 7つの仕事術 [ Shin ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/1353/9784478101353.jpg?_ex=128x128)
コピー1枚とれなかったぼくの評価を1年で激変させた 7つの仕事術 [ Shin ]
- ジャンル: 本・雑誌・コミック > ビジネス・経済・就職 > その他
- ショップ: 楽天ブックス
- 価格: 1,512円
たった1年で「ド落ちこぼれ」が外資系コンサルティングファームのマネージャーになれた!
キレイゴト抜きの、本当に成果が上がる超実践的ノウハウ!!
外資系コンサルティングファームでマネジャーとして勤務し、月間20万PV超の人気ビジネスブログ「Outward Matrix」も運営する若手コンサルタントの処女作!
なぜ仕事ができないのか

- 吸収力:指摘されても「右から左」状態
- 主体性:振られた仕事をこなすだけで精一杯
- 目標設定力:自分の現状と課題が理解できていない
- 思考力:何を、どう、深く考えればいいかわからない
- 資料作成力:資料作成の基本が身についていない
- コミュニケーション力:上司と良好な関係が築けない
- 生産性:1つの仕事にとても時間がかかってしまう
1.「吸収力」を上げよう

「吸収力」と聞いて私たちがよくやるのがメモを取ること。「吸収力」という観点から見ると、メモほど無意味なものはありません。メモを取ってメモを取って満足し、そのままになっていれば意味がない。吸収して初めてメモの意味がある。
指摘のドラフトメール一元化
- 大切なのは、「指摘事項を全て書き留める」ことです。ダブりも気にしない。
- ダブりのある指摘は特に自分が苦手としていることだから
- 自分の言葉で指摘をまとめ直す
- 自分の言葉で再構築し、具体例も付け加える
- 自分の言葉で再構築することは、その指摘の本質を理解することであり、具体例を付け加えることは応用を考えることです
- 見返しのマイルールをつくる
- ドラフトメールを見返すタイミングを意識的に設定しておくことが大切
- 見返しのマイルールを決めておく
- ドラフトメールの内容を誰かに話す
- 誰かに話そうとするとき、その内容の論理を再整理することができます。
2.「主体性」を上げよう

親鳥の餌を待ちわびるヒナに未来はない
上司から与えられた仕事は即座にこなし、余った時間で「もっとこのプロジェクトを良くするためにはどうしたらいいだろうか」」と考え、思いついたアイデアはすぐに実行に移していく。
積極的で仕事ができる人、積極的でも仕事ができない人
積極的な態度とは?
- 仕事に付加価値を付け加えられているかどうか
- 与えられたタスクに新たな価値を付加できる真に主体性のある人
引っ込み思案でもできる主体性の身につけ方
振られた仕事の目的を聞く。たったそれだけで、彼は仕事に新たな価値を生み出し、上司の評価を上げていたのです。
スポンサードリンク
3.「目標設定力」を上げよう

- 抽象的で振り返りづらい目標を立てているといつまでたっても成長できない。
- 正しい目標設定をすると、自分の成長を日々実感しながら仕事に取り組める状態に変わる。
急成長のカギは「目標設定4点セット」
- 目標設定とは定量化=数値化
- KPI(Key Performance Indicator)化
- 定性的なゴールを細かく砕いて数値化し、それを一定期間ごとに振り返って達成できているかを確認する。
- 目標設定に4点セット
- 1.心から達成したい定性的な目標を設定する
- 2.KPI化する
- 3.アクションを定義する
- 4.効果的に振り返る
- どんなにいい目標でも、やりたくなければ達成できない
- 目標をKPI化しよう
- 目標の要素を細かく砕く
- 全てを数値化する
- 現在の実力値の1.3倍がオススメ
- 「アクション定義」でやるべきことを見える化
- 目標を詳細な行動に落とし込む
- 最も効果的な「振り返り」のやり方
- あなたの成長を後押しするダメ押しの一手が「振り返り」の実施
- 頻度は「1週間に1度」
- 毎週確認すべきは、目標ではなく「アクション」
- 定量化した目標の進捗も、1ヶ月に1度は確認します
- しっかりアクションができているのに数値の進捗が悪い場合は、アクションが誤っている可能性が高い
「思考力」を上げよう

思考が深まる「5つの言葉」
- 具合的には?
- 思考を一歩前に進める「具体的には?」 <li思考がまとまらない大きな原因の一つは、「抽象的で曖昧」なことを、曖昧なまま考えていること
- 「悩んでいる」状態を「考えている」状態にするには、具体化することです。
- 理想は?
- 思考の方向性を定める「理想は?」
- 最終的に目指すべきところを明確にすることで、「そこに向かって銅走ればいいのか」と自動的に思考がクリアになっていきます。
- そもそも
- 思考の迷走を止める「そもそも」
- 課題に対して「そもそも、なぜ〜なのか」と、本質を問うことで、適切な方向で思考を深められる。
- 一言で言うと?
- 思考を整理する「一言で言うと?」
- 散在した情報を一度まとめる必要があるとき
- なぜそう言えるのか?
- 思考の質を高める「なぜそう言えるのか?」
- 「なぜそう言えるのか?」と考えると、より高いレベルに思考を導くことができる。
「適切な解」を導きだすための、良質な経験の積み重ね方
- 適切な解を導き出すために必要なのは、絶対的な「経験量」
- ただし、だだ経験が多ければ良いのではなく、「良質な経験」を積み重ねること
- 効果的なのは「ブログ」の執筆
- 自分の言葉で残しとくと、経験が自分の中に蓄積されていく
- ブログは人にわかりやすく書くことを前提としているから
「資料作成力」を上げよう

まずやるべきは、資料全体の目的を明確にし、一連のストーリーを作ること
- 資料の質は”スタート”で決まる
- 読み手に行動を起こさせることが目的
スケルトン作成
- スケルトン=資料の設計図
- スケルトンを作成し、上司に見せ、それから実際の資料を作成する
スケルトン作成の黄金ルール
①現状把握→②原因究明→③打ち手の立案という3つのステップ
- 現状把握
- 現状を明確にすることで、原因も明確になり、打ち手も的を射たものになる。反対に言えば、ここがしっかりできていないと、その後に続く資料もすべて的外れなものとなってしまう。
- 原因究明
- よく見かけるのが、現状把握が終わった瞬間に「打ち手の立案」に行ってしまうパターン。
- 例)売上が下がっている事が分かった(現状把握)
- →営業要因をたくさん増やそう!(打ち手の立案)
- 特定の商品・サービスの売上が下がっていないか?
- 特定の地域・販売拠点での売上が下がっていないか?
- 特定の月で売上が下がっていないか?
- 商品Xの売上が下がった理由は、競合が似たような商品を出したからだろうか?
- 特定地域Aで売れない理由は、地元に根付いた競合商品◎◎の存在だろうか?
- 例)退職率が他の会社と比べてかなり高い水準に達している(現状把握)
- →給料をもっと上げよう!(打ち手の立案)
- 打ち手の立案
- 「どのくらい効果があるか」「どのくらい実行しやすいか」という2つの軸でマッピングし、実行の優先順位をつける
「コミュニケーション力」を上げよう

上司に信頼される質問の作法
- やってはいけないのはアバウトな「オープンクエスチョン」
- 例)この資料の作り方がわからないのですが、どうしたらいいですか?
- 例)クライアントからこんな問合せが来ましたが、返信はどのようにしましょう?
- なぜやってはいけないの?→少しは自分で考えろよ!
- 自分で考えきったうえで、クローズドクエスチョンで質問する
- 例)このようなイメージで資料作成を進めたいのです
- 例)クライアントからの問い合わせに、このような文面で返信しようと思いますが、よろしいでしょうか?
会話は全て「◯◯さん」から始める
人は自分の名前には愛着があり、その名前をあり、その名前をたくさん呼んでくれる人に親近感を持つ
「生産性」を上げよう

生産性が上がらないたった一つの理由
やるべきことを1日の詳細なスケジュールに落とし込めていなかった。
いかがでしたか?
処女作とはとても思えない中身の詰まった、それでいて読みやすい構成で書かれた素晴らしい1冊でした。
おそらく私の読んだ今年のベスト3には入るでしょう。
では!